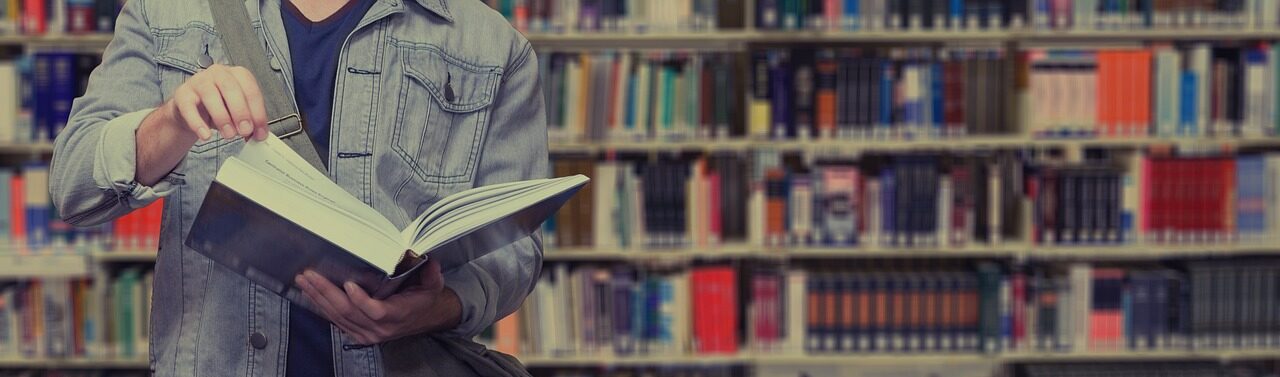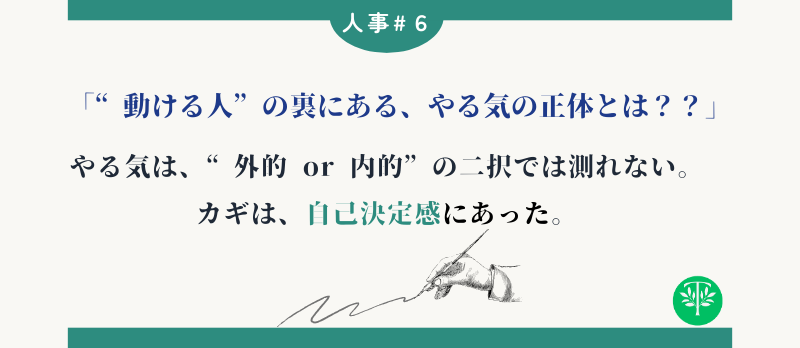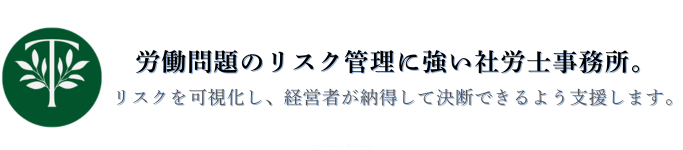【note連載】“動ける人”を制度で育てる──自己決定理論で見る3つの設計ポイント
「給料や評価で人を動かすのは限界がある」──経営者なら一度は感じたことがあるはずです。
しかし報酬は、必ずしも“やる気を壊す”だけではありません。
使い方次第で、内的動機づけを高める“支え”として機能させることができます。
外的と内的の間にある“グラデーション”
人のやる気は「外的」か「内的」かの二択ではなく、その間にグラデーションがあります。
たとえば、上司から言われて参加した研修でも「自分の成長になる」と思えればモチベーションは高まります。
この“納得感のある外的動機づけ”をどう支えるかが制度設計の鍵です。
自己決定理論の3要素
心理学者デシとライアンは、人が自発的に動くために必要な条件として次の3つを挙げています:
● 自律性:「自分で選んでいる」と感じられること
● 有能感:「できるようになった」と実感できること
● 関係性:「誰かとつながっている」と感じられること
制度で支える具体策
経営者がすぐに取り入れられる工夫には、例えばこんなものがあります:
・仕事のゴールや背景を伝え、方法は任せる(自律性)
・小さな成長や工夫をフィードバックする(有能感)
・成果だけでなく貢献や努力を言葉で伝える(関係性)
外的報酬を「ごほうび」ではなく「支え」として届けることで、やる気の重心を外から内へシフトさせることができます。
制度は“人を動かすための道具”ではなく、“信頼を支える土台”。
外的と内的の間をどう設計するか──詳しくはnoteで解説しました。