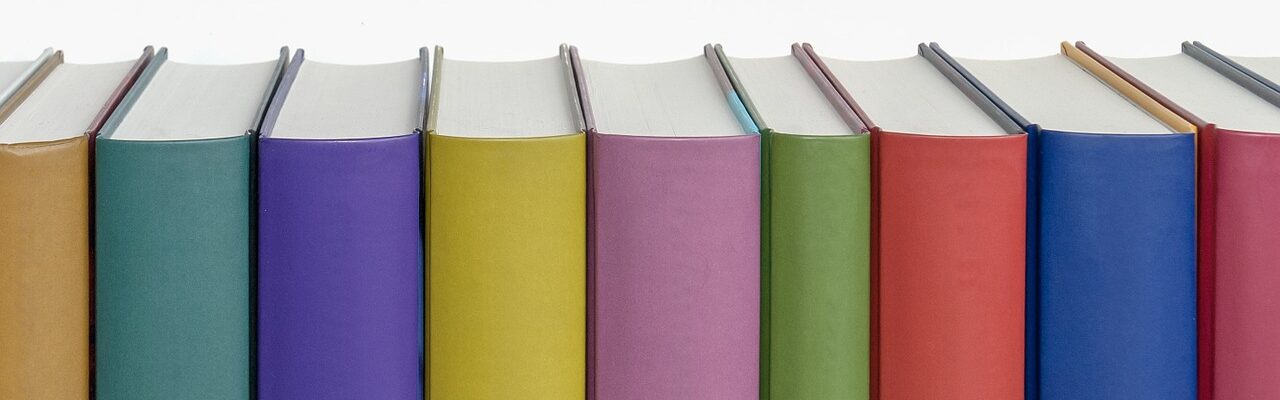
-
お電話でのお問い合わせはコチラです080-5678-1384
- ご相談予約
お電話でのお問い合わせはコチラです080-5678-1384
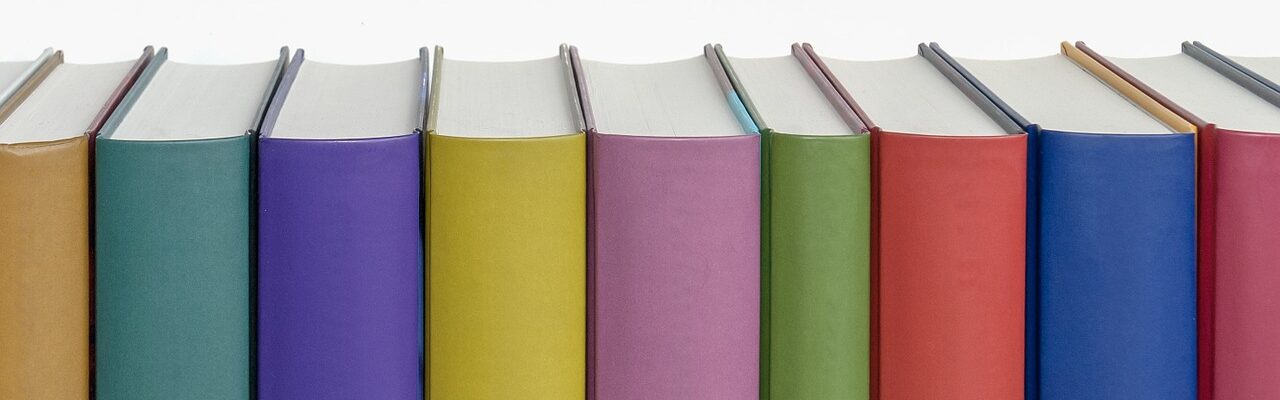

判断に迷ったとき、誰にどう相談すればいいか分からない──
そんな経営者のそばで、“制度”ではなく“関係性”を整えるのが、私たちの役目です。
何かが起きてからではなく、「これって大丈夫?」と思った段階で声をかけられる。
そんな存在がいることで、リスクも気持ちも整えやすくなります。
当事務所では、以下のような“安心感”を、日々の経営のそばにお届けしています。
✅ 迷ったとき、すぐに聞ける
「これって大丈夫かな?」と思ったときに、気兼ねなく相談できる安心感があります。
✅ ひとりで抱えなくていい
不安や迷いを、経営者ひとりで抱えずにすむ関係性が、すぐそばにあります。
✅ 判断の重さを支えてくれる
重要な判断を迫られたときにも、一緒に状況を整理し、冷静な選択ができるよう伴走します。
日々の経営で、迷いが生まれたときこそ、お声がけください。
“正しさ”よりも“安心”を一緒に考える──それが、私たちがそばにいる理由です。
どんなに制度が整っていても、最後に決めるのは“人”です。
その人が、ひとりで悩まなくてすむように──私たちは、そばにいます。

「きっと大丈夫」「たぶん問題ない」「まさかうちが」──
そうやって見過ごされてきた“リスクの芽”が、
ある日突然、許認可取消や損害賠償の形で表面化します。
それが引き金となり、経営が止まってしまうケースは決して珍しくありません。
制度の“ほころび”は、多くの場合、当事者には気づきにくいものです。
「どこか引っかかるけど、大丈夫だろう」──そう思ってきた方こそ、一度立ち止まって点検してみる価値があります。
こうした“見えにくい地雷”を放置したままでは、いざという時に身動きが取れなくなります。
その前に、第三者の視点で現状を点検し、リスクの有無を客観的に可視化することが重要です。
当事務所では、刑事・行政・民事の3領域から構成される労務リスクチェックリスト(全30項目)を用い、“どこに危険があるか”を明確にし、会社の土台を守るための体制
を整えるお手伝いをしています。
まずは、“今のままで大丈夫か”を一緒に点検してみませんか?

労働基準監督署・年金事務所・労働局――
多くの企業が「うちは大丈夫」と思っていても、調査通知ひとつで“整っていない現実”が明るみに出ます。
とくに中小企業では、「何から手をつければいいか分からない」「社労士に頼むのは初めて」という状態も少なくありません。
だからこそ当事務所では、書類の準備だけでなく、実態ヒアリング・行政対応・再発防止の支援まで、一貫して行っています。
調査対応とは、単なる「資料提出」ではありません。
実態との整合性を図り、必要があれば行政側へ合理的な説明を行う──そんな“調整力”が求められる実務です。
実際にご相談いただくのは、「調査通知が届いてから」というケースがほとんどです。
「このままではマズい」と感じた段階でこそ、落ち着いて状況を整理し、適切な対応を始めることが重要です。
調査には“対象として選ばれやすい会社”に共通する特徴があります。
では実際に、どういった理由で調査が入るのか──実務の中で見えてきた主な“きっかけ”を紹介します。
こうしたリスクは、多くの企業で気づかないうちに積み重なっていることがほとんどです。
たとえ小さなミスでも、発覚すれば2年分の各種保険料の遡及清算や是正指導などが発生し、
金銭的な負担や現場の混乱、信用面での影響につながります。
そして一度調査対象になると、「そういう会社」として再調査リストに残りやすくなるのも現実です。
“ズレ”に気づいた今が、仕組みを整えるチャンスです
行政調査は「ピンチ」ではなく、仕組みを見直すきっかけでもあります。
スポット対応はもちろん、その先の“整える支援”まで一緒に取り組みましょう。

「3年分の未払い残業代を請求された」
実際に、そうした事例は少なくありません。
勤怠管理に不備があると、行政調査や労働審判・訴訟の場で企業が“実質的に証明責任を負う”構図になりがちです。
たった一人の請求でも、数百万円規模の支出リスクがあります。
勤怠管理は、経営の“土台”です。
手書き・Excel・タイムカードといった従来型の管理では、集計ミス・残業計算漏れ・属人化のリスクがつきものです。
当事務所では、こうした課題の根本解決策として、クラウド型勤怠管理システム「キングオブタイム」の導入を提案しています。
打刻・残業・休暇の可視化により、正確で効率的な労務管理を実現できます。
ただし、システムを「入れるだけ」では十分とは言えません。
現場に合った設計と、スムーズな定着支援があってこそ意味があります。
当事務所では、初期設定からルール整備・運用支援まで一貫して対応します。
特に、以下のような企業には、キングオブタイムの導入が効果的です。
「紙やExcelの管理に限界を感じている」
「勤怠の不備が給与・社保にも波及して困っている」
──そんな企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
実情に合った仕組み設計と、安心して運用できる体制をご提供します。

職場には、業務効率や雰囲気を損なう「問題社員」の存在が、避けがたい現実としてあります。
ローパフォーマー、ハラスメント、命令違反、横領、私生活でのトラブルなど、種類も深刻さもさまざま。
一人の対応を誤れば、現場の空気が悪化し、周囲の従業員が離職する──そんな連鎖が、組織の信頼や経営判断にまで影響を及ぼすこともあります。
このような対応には、「感情」だけでも「法律」だけでも足りません。
解雇無効リスクや関係悪化を避けるには、法的根拠と人間理解の両立が欠かせないのです。
また、本人への対応だけでなく、周囲の不満や不信感を最小限に抑えることも、企業としての重要な視点です。
当事務所では、事実のヒアリングや対応方針の整理はもちろん、
問題の性質に応じて懲戒以外の柔軟な手法や、再発防止の仕組みまでサポートしています。
例えば業務日報は、単なる記録ではなく、本人の“認知のゆがみ”に気づかせる手段として活用可能です。
また、私自身がかつて問題社員だった経験から、伝わらない理由や反発の背景にも深く目を向けています。
問題が複雑だからこそ、感情に振り回されず、軸を持った対応が必要です。
当事務所では、以下のような視点から、状況に応じた現実的なサポートを行っています。
一人の対応が職場全体の空気を変えてしまうこともあります。
感情に流されず、制度に偏りすぎず、冷静な打ち手を一緒に考えていきましょう。

従業員の病気やケガ、メンタル不調による休職は、いまや珍しくありません。
だからこそ、企業には「制度と現場」両面からの丁寧な対応が求められます。
一方で、制度の整備が不十分なまま個別対応を続けると、
休職の開始・延長・復職・退職といった各場面で混乱が起こり、
労使間の信頼を損なうリスクや、後のトラブルへと発展する危険もあります。
とくに自然退職(休職期間満了)と判断した対応が、労働審判・訴訟で無効とされる場合、未払い賃金の支払義務が生じたり、予期せぬ復職によって現場が混乱することもあります。
当事務所では、休職開始から復職までのプロセスを見通したうえで、
制度設計や社内ルールの整備、対応体制の整理までサポートしています。
対応の要は、本人への誠実な配慮と、企業としての一貫性にあります。
ときに「何を言っても休める」といった誤解や、“権利の濫用”ともとれる主張に、現場が振り回されることもあります。
企業としての優しさと毅然さ、その両方の姿勢が、職場全体の信頼を守るうえで不可欠です。
当事務所では、以下のような視点から、実情に応じた現実的なサポートを行っています。
「ルールがなくて、毎回その場しのぎ」
そんな状態では、判断の迷いがいずれ大きなトラブルに。
まずは「戻れるかを見極める最低限の土台」を整えましょう。
今こそ、“なんとなく対応”を卒業するタイミングです。