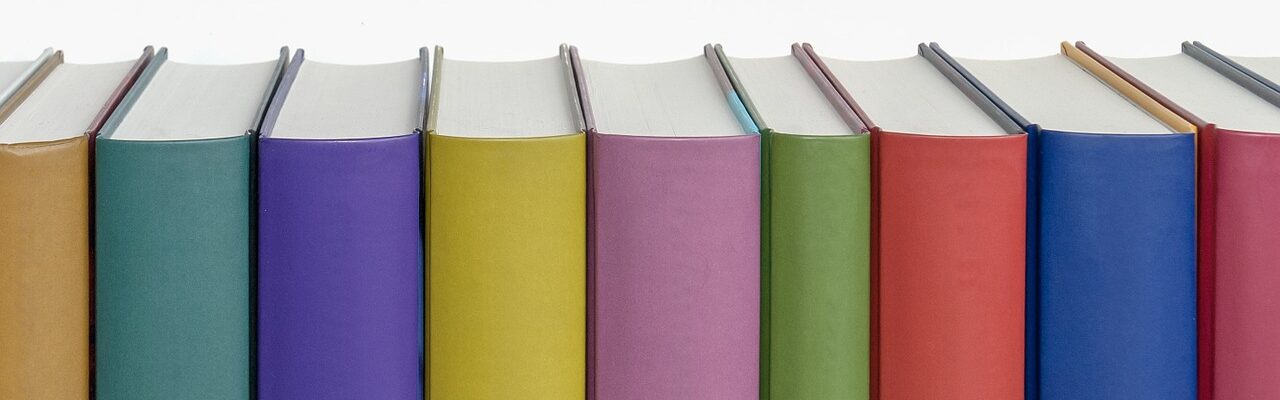
-
お電話でのお問い合わせはコチラです080-5678-1384
- ご相談予約
お電話でのお問い合わせはコチラです080-5678-1384
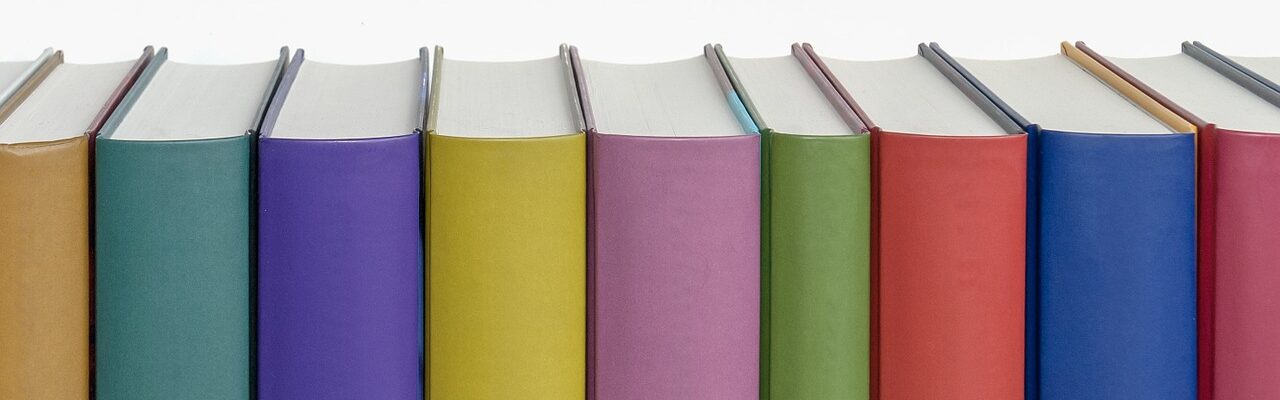

「給与ソフトがあるから安心」と思っていませんか?
本当に重要なのは“設定”と、その前提となる法的判断です。
たとえば、残業代の計算方法や社会保険料・所得税の算出も、法律の解釈が違えばすべてズレてしまうのです。
当事務所では、以下の支援を行っています:
✅ 給与体系のチェック(会社の意図と法解釈が交わるポイント)
✅勤怠集計と社会保険料・税金の整合レビュー
✅ 規程との連携調整(就業規則・賃金規程)
給与まわりの相談相手がほしい
──そんな方へ、制度と運用の“ずれ”を整える土台づくりをご支援します。

社会保険手続きは、各様式に合わせて正確に作成する必要があります。
ネットで調べながら手続きを進めることはできますが、「うちの場合はどう書けばいいのか…」と迷いませんか。
とくに、以下のような場面では、ネット情報だけでは対応しきれないことがあります:
当事務所では、社会保険手続きを熟知したプロが電子申請を活用し、迅速かつ正確に対応します。
手続きの負担を減らし、本業に集中できる環境を整えます。

就業規則がない会社は、いわば“ルールのない国”。
トラブル時に「何を根拠に判断するか」を示せず、経営者も従業員も迷子になります。
結果、感情やその場の空気で判断せざるを得なくなり、納得感や一貫性を欠いた対応に陥りがちです。
入社、雇用形態の変更、休職・復職──
そして懲戒処分、解雇、雇止め、退職…。
揉めやすい局面こそ、就業規則の条文が会社を守る“最後の盾”になります。
就業規則を整えていないことで、よくあるのはこんな場面です:
ルールがないまま“運に頼る経営”を
続けますか?
就業規則を整えれば、採用~退職まで――
迷いがちな労務判断を、頼れる“軸”を持って進められます。
まずは軽いヒアリングから、
気になる点を一緒に整理してみませんか?
真剣なご相談は、しっかりとした体制で有料対応いたします。
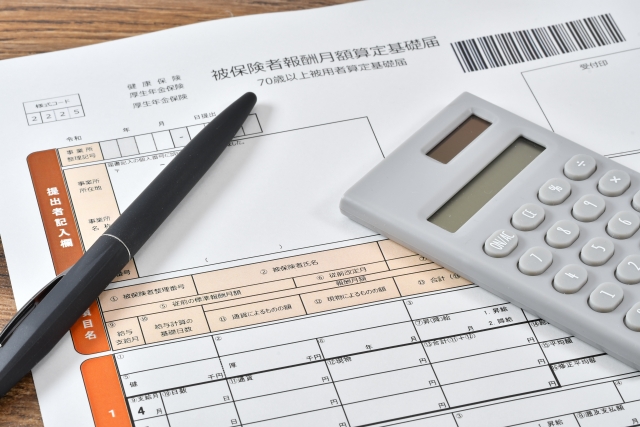
算定基礎届とは、社会保険加入者(役員・アルバイト・パートを含む)の4月〜6月に支払われた給与をもとに、社会保険料を見直す年1回の手続きです。
しかし、制度を正しく理解しないまま「形式的に提出しているだけ」になっていたり、そもそも「うちは対象外だと思っていた」といった声も少なくありません。
たとえば、1人社長の法人でも社会保険に加入していれば提出義務はあります。
過去に、算定基礎届を2年間提出していなかったことで、定期調査の依頼が届き、結果的に過去分の対応を迫られたケースがありました。
その際、年金事務所の担当者は「出していない法人ほど優先的に確認対象になります」と明言しており、
「人が少ないから関係ない」は通用しない現実があります。
また、算定をきっかけに、日々の社会保険手続きの漏れや誤りが浮き彫りになることもあります。
たとえば、次のようなケースです:
これらの多くは、原則として過去2年分の社会保険料を遡って清算することになります。
とくに従業員負担分の取り扱いについては、後から請求するとトラブルになることもあり、「会社が全額を負担せざるを得ない」ケースも実際にあります。
社会保険まわりの手続きや判断に迷ったとき、安心して相談できる相手がいる。
──そんな体制を、いまのうちに整えておくことが大切です。

労働保険料の年度更新とは、1年間に支払われた給与をもとに、労働保険料を精算する年1回の手続きです。
アルバイト1人でも給与を支払っていれば提出義務があり、「うちは関係ない」と思っていたという声も少なくありません。
給与の集計作業だけが大変と思われがちですが、正社員・アルバイト・日雇い・役員・出向者・海外赴任者など、「雇用形態や就労形態」や「雇用保険の加入状況」などに応じて、集計対象となる給与と対象外の給与を正確に見極める必要があります。
また、普段の給与計算を税理士に任せている場合でも、労災保険や雇用保険や社会保険の「適用判断」は専門外のため見られていないことが多く、
年に一度の年度更新で“積み上がった見落とし”が表面化するケースも少なくありません。
たとえば、次のようなケースです:
こうしたリスクは、気づかないうちに積み重なっていることがほとんどです。
小さなミスでも、発覚すれば2年分の遡及清算や行政からの指摘・対応要請につながることもあり、
金銭負担や行政対応、信用リスクがのしかかります。
一度見つかれば、「そういう会社」として今後の調査対象になる可能性も。
「ただの集計作業」で終わらせず、会社全体の“抜け”を見直す機会にしませんか?

「手当を廃止したい」「固定残業代を見直したい」「休暇制度を変更したい」──
でも、“不満や反発が出るのでは…”と、なかなか踏み切れない経営者も少なくありません。
こうした“従業員にとって条件が下がる変更”は「不利益変更」と呼ばれ、慎重な進め方が必要です。
「このままで大丈夫かな…」と感じながらも、どう進めていいか分からない──そんな段階でのご相談が、実はいちばん多いです。
制度を見直すうえで大切なのは、従業員の「納得感」です。
どんなに正当な理由があっても、「損をした」と感じさせてしまえば、不満や反発は避けられません。
納得感を支えるのが、代償措置や経過措置です。
実務では、手当を廃止する際に金銭面での補填や、福利厚生など非金銭的な価値への転換がポイントになります。
たとえば住宅手当を基本給に組み込む、家族手当の代わりに福利厚生を充実させるなど、「下げただけではない」配慮設計が重要です。
書類(就業規則や通知文)は、その設計意図を正しく伝えるための道具です。
進め方を誤ると、従業員の反発だけでなく、民事紛争に発展するケースもあります。
実際、賃金や休日といった重要な条件の変更が「無効」と判断される例は少なくありません。
制度変更は、「何を変えるか」よりも、“どう伝え、どう整えるか”が成否を分けます。
迷ったときは、まず状況を整理するところから始めてみませんか?
当事務所が、背景の整理や就業規則の整備を通じて、安心できる制度設計をサポートします。