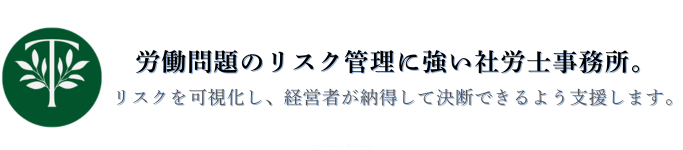ご相談・業務依頼をご希望の方へ
“なんとなく不安だけど、何から手をつければいいかわからない”——
そんな状態でも大丈夫です。まずは、いまの状況を一緒に整理するところから始めましょう。
🔍 こんなご相談をお受けしています
「ちょっとしたことだけど、誰に聞けばいいのか分からない」——そんな声から始まるご相談も、実はとても多いんです。
🧭 ご提供できる支援内容
企業の課題は、表面化している問題だけとは限りません。
だからこそ、火急のトラブル対応から、人を活かす仕組みづくりまで——
5つのフェーズに分けて、状況に応じた支援を柔軟にご提供しています。
🔥 PHASE 1|スポット対応フェーズ
— “いま起きている困りごと”を、まず何とかしたい方へ
こんな方におすすめです
【事例】サービス業・従業員数30名(退職者からの未払い残業代請求)
● 相談のきっかけ:
求人が集まりにくい理由を探る中で、社長から「最近の求職者は『就業規則はありますか?』と聞いてくる」との相談があった。
制度が“外からどう見られているか”を意識し始めたことが、整備のきっかけとなった。
● 実態確認で明らかになった背景:
面談を通じてヒアリングを重ねる中で、退職者から未払い残業代の請求(内容証明)が届いていたことが判明。放置していれば、労基署への通報や訴訟などの深刻なリスクに発展していた。
● 対応と整備の内容:
- ① 規程一式の整備: 就業規則・賃金規程・育児介護規程・労働条件通知書を新規で整備
- ② 未払い残業代の清算: 整備した賃金規程に基づき未払い残業代を算出し、過去分の支払い整理を実施
- ③ 和解交渉と法的対応: 提携弁護士による交渉により、法的リスクの軽減とサポート体制を確保
● 結果:
トラブルの早期把握と制度整備により、訴訟に発展する前に問題を収束。
規程整備を通じて再発防止の体制が整い、
「制度が整っている企業」として採用面での信頼性も向上した。
今回の対応をきっかけに、経営を止めないための制度整備(PHASE 2)への移行も視野に入れ、
リスクの棚卸しや優先順位の整理について、継続的なご相談をいただいている。
トラブルは、いつも“不意打ち”でやってきます。
そんなときこそ、冷静に状況を見極め、ムダなく、今すぐ必要な範囲だけを整えて、次の一手を打てる状態へ。
PHASE 1では、御社の火急の事案や現場の混乱に対して、
「いますぐ状況を見極め、動けることから着手する」ことを軸にしたサポートを提供します。
拙速にならず、急ぐべき時は急ぎ、慎重に進めるべきところは立ち止まる。
その判断を、現場と一緒に行います。
🔴 PHASE 2|倒産リスク整備フェーズ
— “整えていなかった”ことが、会社を止める引き金になる前に
こんな方におすすめです
【事例】情報サービス業・従業員数22名(固定残業代の曖昧運用)
● 相談のきっかけ:
「制度に大きな問題はないと思うが、気になる点がいくつかある」と、社長から診断のご依頼。
話を進めるうちに、何となく感じていた違和感が、制度の“危うさ”として具体化していった。
● 確認の結果、把握された主な課題:
-
社長は「固定残業代を導入すると社会保険料が安くなる」と聞き、制度として取り入れていたが、
制度の趣旨や設計が曖昧なまま、“形だけ”の導入になっていた。 -
その結果、現場では「一律で支給される手当」として定着しており、
実際の残業時間が固定時間を超えても差額の清算がされていないなど、
未払残業代が発生する危険な状態となっていた。
● 想定されるリスク:
- 制度として無効: 固定残業代制度が認められず、「支払っていたつもりの残業代」が未払いと見なされる。
- 単価の上昇: 時間単価が上がることで、残業代の請求総額が膨らむ。
- 付加金のリスク: 裁判になった場合、未払額と同額の付加金を裁判所から命じられる可能性がある。
- 遅延損害金の追い打ち: 年14.6%の遅延損害金(退職後の場合)が上乗せされ、金額的な負担がさらに増す。
● 対応と整備の内容:
- ① 賃金規程を改訂: 固定残業代制度の趣旨、対価とする割増賃金の内容、清算方法を明文化
- ② 労働条件通知書・給与明細の見直し: 固定残業代に含まれる割増賃金の「種類・時間数・金額」を明示し、明確区分性と対価性の2要件を満たす体制へ
- ③ 勤怠システム導入: 実績と固定時間の差分を自動清算可能な体制に
- ④ 書面での同意取得: 過去分の清算と新制度への移行について、全従業員と個別合意
● 結果:
過去の未払いや制度の不備といった“負の遺産”を清算し、
今後同様のトラブルが起きても、説明責任を果たせる体制が整った。
現在は定期的なリスク診断と優先順位の見直しを行うため、PHASE 4(顧問体制フェーズ)への移行を進めている。
「うちは問題ないはず」——そう思いながらも、関心が向きにくい部分や見落としやすい部分に、実は経営を揺るがすようなリスクが潜んでいることもあります。
PHASE 2では、約30項目のチェックリストをもとに、そうしたリスクを客観的に棚卸し。
経営の“足元”を見直すことで、会社を止めないための最低限の備えを整えるフェーズです。
「全部やる」のではなく、必要なところから。
見えにくいリスクを一緒に整理し、将来のトラブルに備える一歩を踏み出してみませんか?
🟡 PHASE 3|行政調査対応整備フェーズ
— “整っているつもり”が、調査で崩れ落ちる前に
こんな方におすすめです
実態とズレていないか、どこか違和感がある。
ネットを見ながらなんとか対応しているが、内容に自信が持てない。
「できれば該当しませんように…」と祈るような気持ちでいる。
【事例】製造業・従業員数20名(労基署の調査)
● 相談のきっかけ:
退職者からの通報をきっかけに労働基準監督署の調査が実施され、
調査対応の経験がなかった社長から「何をどう準備すべきか分からない」とスポット相談を受けた。
● 調査前の確認で把握された主な課題:
- タイムカードはあるが、残業時間の集計や清算がされておらず、結果的に残業代が未払いとなっていた。
- 36協定が古い状態で、現在の働き方に合っておらず、特別条項が抜けていた。
- 健康診断の実施後、異常の所見があるにもかかわらず医師への意見聴取が行われていなかった。
● 想定されるリスク:
今回のケースでは、早期に整備へと踏み切ったことで重大な問題には至らなかった。
しかし、仮にこのまま対応を先送りにしていた場合、以下のようなリスクが現実化していた可能性がある。
- その場しのぎの是正報告: 調査時の指摘に対して帳尻を合わせるような書類対応に終始していた場合、実態との乖離が広がっていたおそれがある。
- 再調査での厳しい指摘: 一度提出した是正内容と実態が一致していなければ、虚偽報告とみなされ行政対応が一段と厳しくなった事例もある。
- 送検・企業名の公表: 度重なる調査で改善が見られない、あるいは虚偽の内容が確認され悪質と判断された場合、 検察へ送致(送検) されるおそれがある。
また、重大な違反と判断されたケースでは、企業名が厚生労働省のホームページで公表された事例もある。 - 許認可・入札資格への影響: 建設業・介護・保育・人材サービスなどの業種では、行政処分歴によって許認可や公共入札資格に影響が出たケースがある。
- SNS・採用・取引先への波及: 調査対応や企業名の公表がSNSで拡散し、採用活動や取引先との関係に悪影響を及ぼした事例もある。
● 対応と整備の内容:
- ① クラウド勤怠システム: キングオブタイムを導入し、打刻・集計・残業実績を可視化
- ② 36協定の見直し: 働き方の実態に合わせて内容を再設計し、毎年の作成・提出を弊所が担当
- ③ 医師所見の運用体制: 健康診断後の意見聴取を確実に実施できるよう、地域産業保健センターを活用
- ④ 書面での同意取得: 未払いの残業代について、対象従業員と個別に同意書を取り交わし清算
● 結果:
“なんとなく”で進んでいた制度運用を見直し、調査で問われるポイントを意識した体制へと再構築した。
今後は突発的な調査や社内変更があっても、根拠をもって冷静に対応できる構えが整っている。
現在は、制度運用の定着と継続的な見直しを支援するため、PHASE 4(顧問体制フェーズ)への移行を視野に入れている。
【事例】不動産業・従業員数12名(年金事務所の調査)
● 相談のきっかけ:
年金事務所からの定期調査通知を受け、「何から手をつければいいのか分からない」と困り果てた社長が、不安を抱えたまま弊所にスポット相談を寄せた。
● 事前確認で把握された主なリスク:
- 社会保険未加入者が複数存在していた。
- 月額変更届(随時改定)の提出漏れが複数あった。
- 週30時間を超えていたパート社員が存在し、加入要件に該当する可能性があった。
● 想定されるリスク:
- 加入対象の取りこぼし・提出漏れ: 社会保険の調査では、加入対象者や月額変更届の漏れが厳しく確認され、原則として過去2年に遡っての手続きが求められる。
- 従業員への説明・精算トラブル: 本来従業員が負担すべきだった社会保険料の精算をめぐって不満が出る、給与天引きの合意が取れないなど、混乱が生じやすい。
- 不要な加入指導のリスク: パート社員の勤務実態を正確に説明できないと、本来不要な社保加入を指導される可能性がある。
- 国保の切り替え・療養費請求: 国民健康保険からの切り替えや、誤って使用した保険証に関する医療費の精算など、従業員側にも煩雑な手続きが生じる。
- 信頼関係の悪化: 発覚時に適切な説明やフォローができなければ、従業員との信頼が損なわれるリスクがある。
● 対応と整備の内容:
- ① 加入対象者の再抽出と提出: 調査前に対象者を再抽出し、必要な月額変更届もすべて提出完了
- ② パート社員の除外立証: 稼働実績データを整理し、一時的な勤務であることを立証。不要な加入を回避
- ③ 社保対応の運用体制: 加入条件と月変基準を社長と共有し、給与改定・手当新設/廃止・働き方の変更時には都度相談を受ける体制へ
● 結果:
事前の見直しにより調査対応の精度が高まり、加入漏れや提出漏れの是正に加え、従業員とのトラブルや精算時の混乱も未然に防止することができた。
こうした対応を通じて、今後も判断に迷わない体制を継続的に整えていきたいとのご意向が生まれ、PHASE 4(顧問体制フェーズ)へと移行する運びとなった。
「制度はあるけど、本当にこれでいいのか?」
そんな違和感を放置していると、いざという時に説明がつかず、信頼を失うリスクがあります。
PHASE 3では、“整っているつもり”の制度や記録を、現場の実態と照らし合わせて点検・整備。
就業規則・労働条件通知書・法定四帳簿・健康診断・ストレスチェックなど、調査やトラブルで確認されやすい項目を重点的に見直します。
見せられる・説明できる状態を平時から整えることで、
突然の行政対応にも揺るがない「信頼の土台」を築きます。
🔵 PHASE 4| 顧問化・継続対応フェーズ
— 点ではなく“線で支える”ことで、判断の迷いをなくす顧問体制を
こんな方におすすめです
【事例】サービス業・従業員数18名(中途採用の女性事務社員が“やっているつもり”で成果が出ない社員への対応ケース)
● 相談のきっかけ:
中途採用した女性事務社員が、「注意しても改善されない」「期待されている仕事を果たせていない」状態が続いていた。
過去にも社員トラブルでスポット相談を受けていた社長から、今回は継続的な支援のご依頼をいただいた。
● 把握された主な課題:
- 本人に「業務をしている」という自覚がある一方で、実際の成果や周囲との認識に大きなギャップがあり、“やっているつもり”が強く表れていた。
- 社長が感情的に対応してしまう場面があった。
- 上司や同僚はパワハラを恐れて静観的となり、現場での指導が機能していなかった。
- 初動の対応が甘く、注意すべき行動を見過ごしてしまった結果、トラブルが長期化していた。
- 指導や注意の記録が曖昧で、対応が形式的・感覚的になっていた。
● 想定されるリスク:
- 選択肢の不足による対応の偏り: 懲戒解雇・普通解雇といった強い手段に対応が寄りがちになり、業務再設計・配置転換・雇用契約の見直しなど、柔軟な対処策が検討されず、対応が硬直化する。
- 「解雇ありき」と見なされるリスク: 指導記録があっても、他の選択肢を検討していない姿勢が伝われば、解雇無効・未払い賃金(バックペイ)の支払い命令に繋がる可能性がある。
- 関係性の悪化が長期化: 問題の長期化により、モチベーションや信頼感に影響し、職場の空気が悪化する。
- 労働組合・労基署・弁護士への駆け込み: 従業員が外部機関に相談し、社内対応で収まらないリスクが生じる。
● 対応と整備の内容:
- 業務日報や指示書の活用: 現実とのギャップに気づいてもらい、認知の歪みを修正していった。
- 業務指導書や注意書の交付: 状況を正確に伝える対応を重ねた。
- 記録・整理による冷静な判断: 指導の型を整え、感情に振り回されない対応が可能に。
なお、業務日報や面談は、ただの“記録”ではありません。
向き合う姿勢そのものが、関係性のこじれをほぐし、本人に現状を自覚させる“太陽”のような役割を果たします。
事実を丁寧に伝え続けることで、「やっているつもり」と「求められている行動」とのズレ──つまり認知の歪みに、本人が気づき始めます。
強制ではなく、理解と納得へ導くことが、制度の真価だと考えています。
● 結果:
業務日報や面談を通じて、本人も現状を受け止める形となり、関係性の整理に至った。
無理に引き止めることなく、現場の空気も早期に落ち着きを取り戻し、社長の不安も軽減された。
その後も状況を見守りながら、判断に迷わないための「指針と型」を軸とした支援を継続している。
スポット対応では、毎回のご相談ごとに背景の説明が必要となり、
その都度「なぜ今こうなっているのか」を一から整理することになります。
顧問の場合は、過去の経緯や社内の変化を継続的に把握しているため、
前提の共有を省略でき、判断もスムーズかつ一貫性を持って行うことができます。
PHASE 4では、スポットでは見えにくい「全体の地図」を一緒に描き、
日々の小さな変化や法改正にも対応できる“使いこなす制度”の土台づくりを支援。
経営と現場の橋渡し役として、過去・現在・未来をつなぐ顧問体制をご提案します。
🟢PHASE 5:人材グロース設計フェーズ
— 成長を止めない組織づくりのために、人の流れを設計するフェーズ
こんな方におすすめです
【事例】福祉事業・従業員数18名(採用のミスマッチ改善支援)
● 相談のきっかけ:
ハローワーク中心の採用で、社長の感覚に頼った面接・評価が続いていた。
6ヶ月以内の離職が続き、定着率の低さが「偶然なのか」「仕組みの問題なのか」判断できず、
自社の採用と受け入れのあり方を見直すべきか悩んでいるとのご相談をいただいた。
● 把握された主な課題:
- 入社前後の受け入れ対応が場当たり的で、雇用条件が曖昧なまま入社するケースが続いていた。
- 初期対応に必要な項目(健康状態の把握、反社チェック、内定承諾書、行動規範)が未整備で、労務リスクが放置されていた。
- 求人票の内容が抽象的で、応募者とのミスマッチが多く見受けられた。
- 面接時に見る視点が定まっておらず、価値観のズレを見抜けないまま採用してしまうことがあった。
● 想定されるリスク:
- 初期ルールの不整備によるトラブル: 健康状態の申告や反社チェックが未実施の場合、採用後のトラブル(体調不良・不祥事など)に対する会社の対応力が問われる。
- 就業意識のズレによる問題行動: 行動規範の共有や誓約なしで入社させた場合、「指導したつもりでも伝わっていない」「禁止行為を止められない」といった現場での統制が難しくなる。
- 情報管理・競業リスク: 誓約なしで入社させた場合、退職後の情報漏洩や競業行為に歯止めが効かず、会社の信用や事業継続に支障が出る可能性がある。
- 心理的なコミットの欠如: 入社承諾書などで入社意思を明確にしないまま迎えると、組織との関係があいまいなままスタートし、早期離職や無断辞退のリスクが高まる。
- 早期離職による採用コストの増大: 雇用条件のすり合わせが曖昧なまま入社し、短期間での離職が続けば、採用コストや職場の疲弊を招く。
- “口約束”によるトラブル: 入社条件や業務内容が明文化されておらず、「聞いていない」「そんなつもりじゃなかった」という認識ズレが不満や混乱につながる。
- 組織内の信頼低下: 毎回“その場しのぎ”の採用と定着対応になると、既存社員の信頼も揺らぎ、定着率全体の低下を招く可能性がある。
● 対応と整備の内容:
- 入社前後に必要な書類を整備: 健康状態告知書/反社排除誓約書/内定承諾書/入社誓約書
- 労働条件(給与・社保・勤務形態)の事前確認: 入社前にすり合わせを行い、トラブルの芽を摘んだ
- 「どんな人(ペルソナ)と働きたいか」を社長と対話し言語化
- 求人票を修正: 期待行動や組織の想いを反映
- 面接時の確認視点を整理: 面談シートを整備
● 結果:
定着のための初期対応が機能し始め、離職傾向に明らかな変化が見られた。
求人票や面接の改善により、本命ではない応募者のエントリーが減少し、面接段階でのミスマッチも減った。
受け入れ時の抜け漏れが減少し、安心して迎え入れられる体制が整ったことで、社内の受け入れ側にも余裕が生まれつつある。
今後は、育成や評価といった“次のステップ”を見据え、組織の成長に向けた土台づくりを進めていく予定である。
「人事制度」と聞くと、“きちんと整えないといけないもの”と捉えがちです。
けれど本当に必要なのは、「誰と働くか」「どう迎え入れるか」を見定める目線と、その土台を整えることです。
人事制度と求人、どちらが先かは“鶏と卵”のような問いかもしれません。
ただし中小企業では、制度だけ先に整えても形骸化するリスクが少なくありません。
だからこそ、私たちは「人事制度の前に、採用の設計」を提案します。
どんな人を求めているかを明確にした上で、求人票・面接・意思確認・条件すり合わせ──まず“すれ違い”を防ぐ仕組みを、無理なく実務に落とし込むことから。
それが、人事制度に頼らなくても“人の動きが整っていく”実感につながります。
あなたの組織らしさを活かした初期対応を、共に設計する支援を行っています。
📝 ご相談の流れ
- フォームからご連絡(無料) — 不明点やざっくりした悩みでもOKです。
- ご相談実施(30〜60分) — Zoom・電話・メール等、ご希望の方法で柔軟に対応します。
- 必要に応じた対応方針のご提案 — ご相談内容に応じて、後日対応または継続サポートのご案内をいたします。